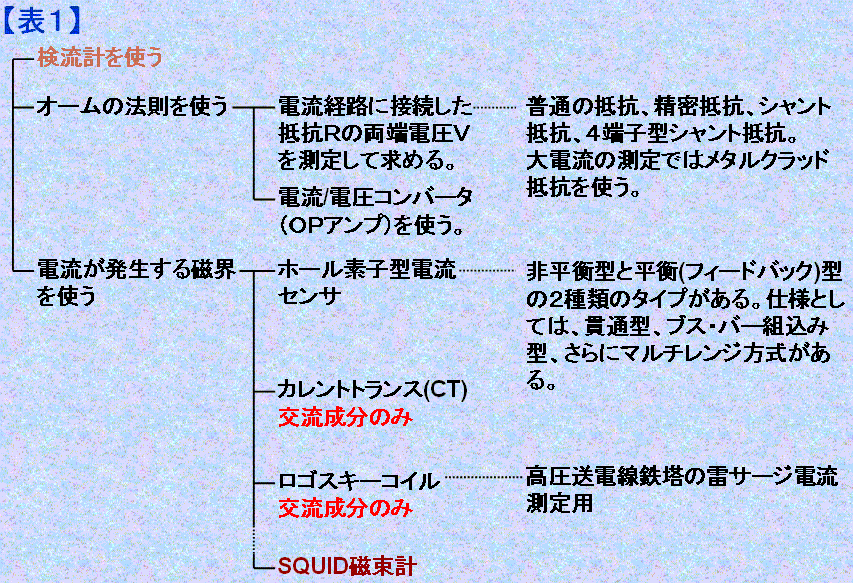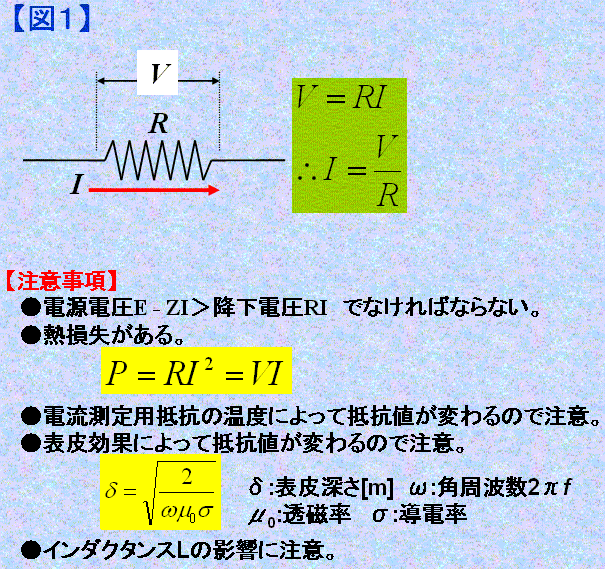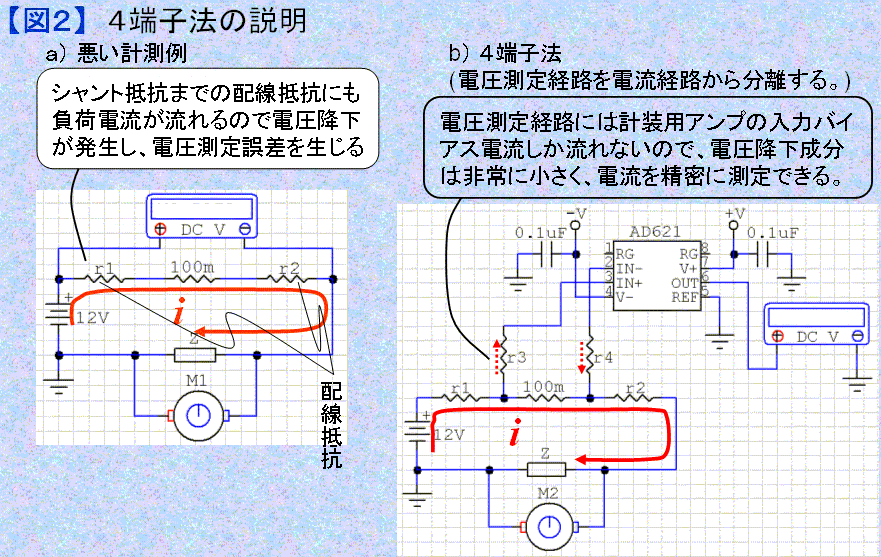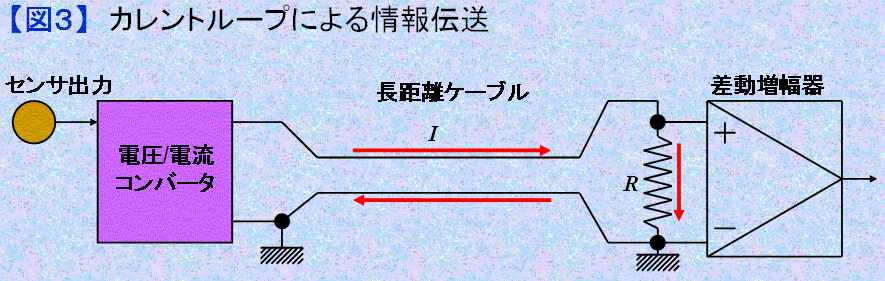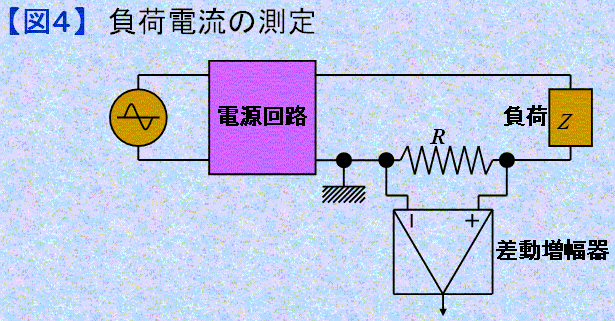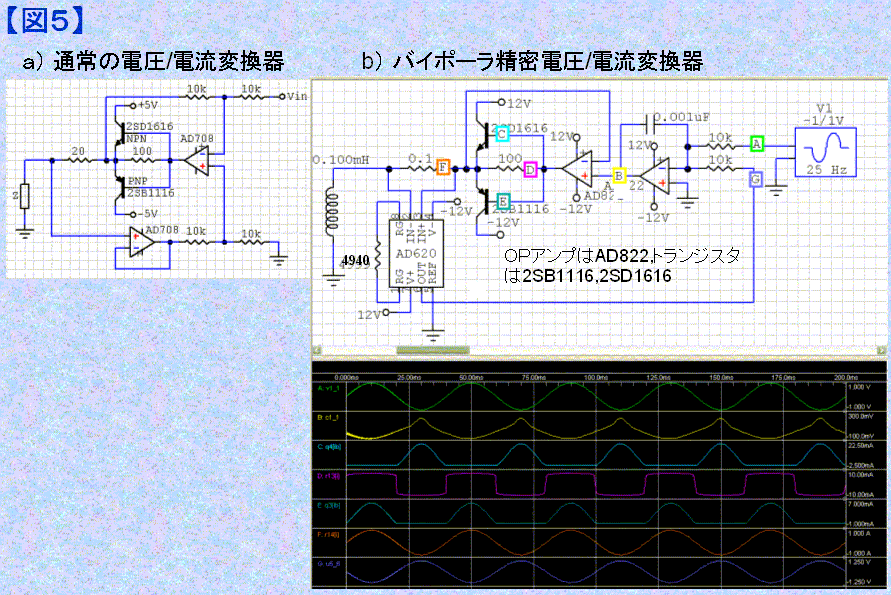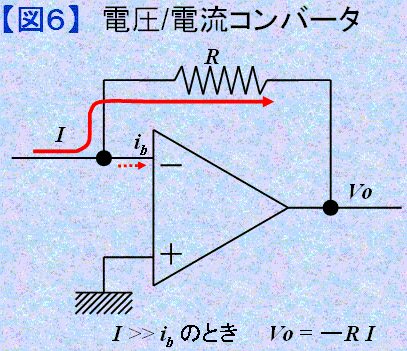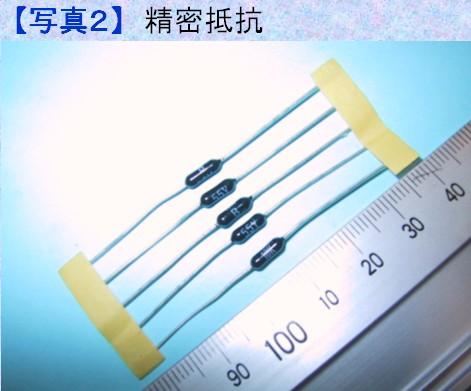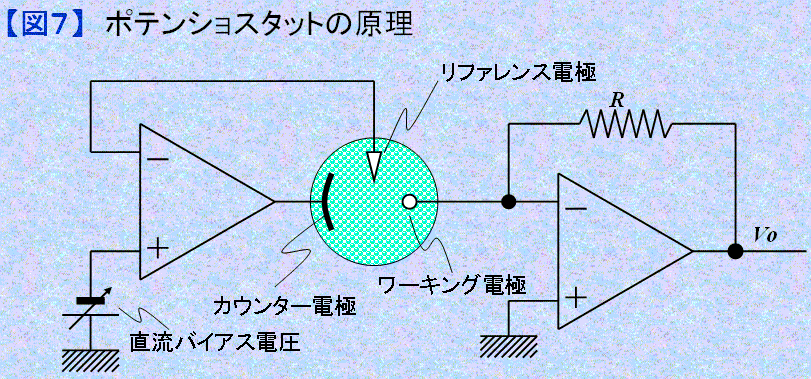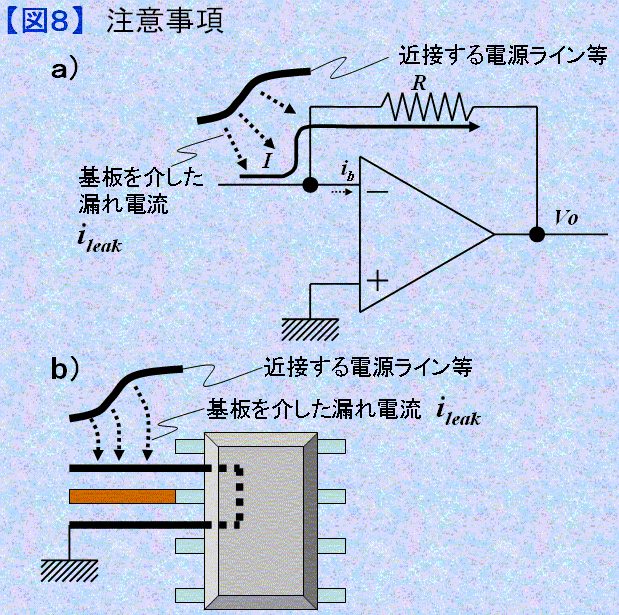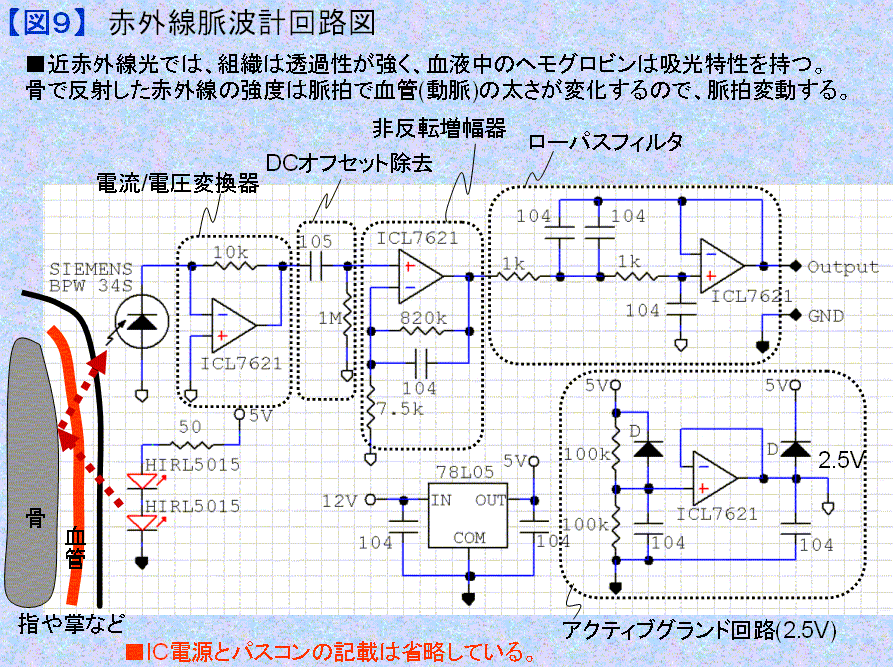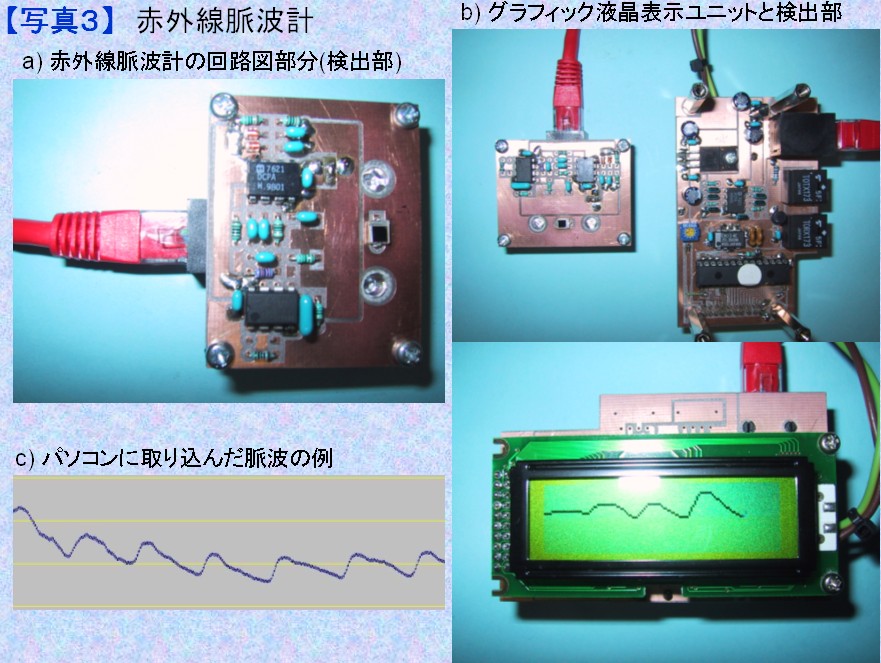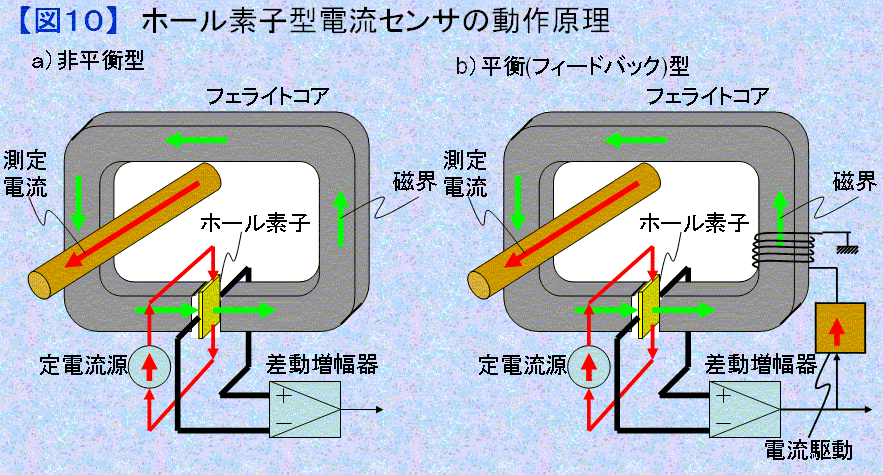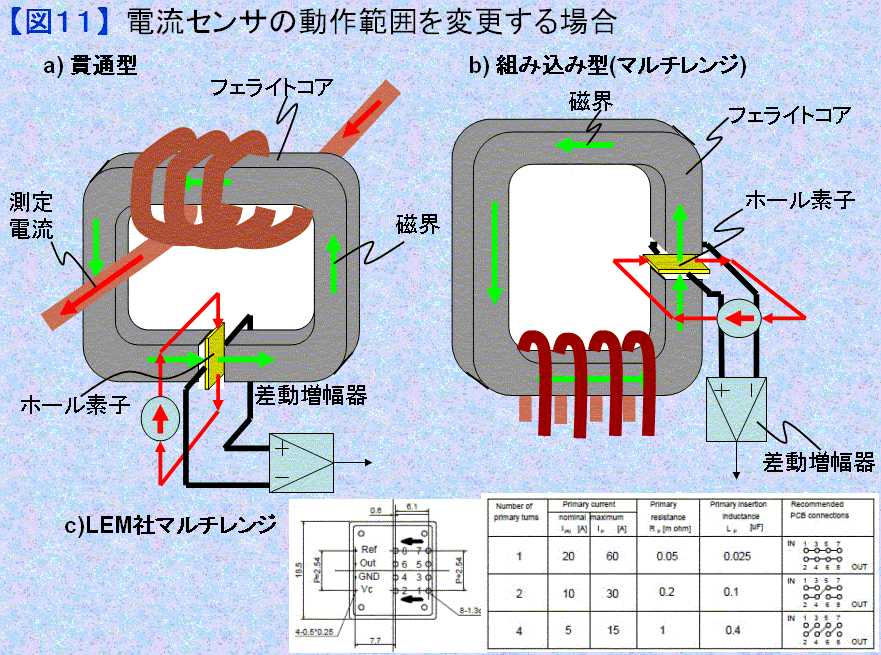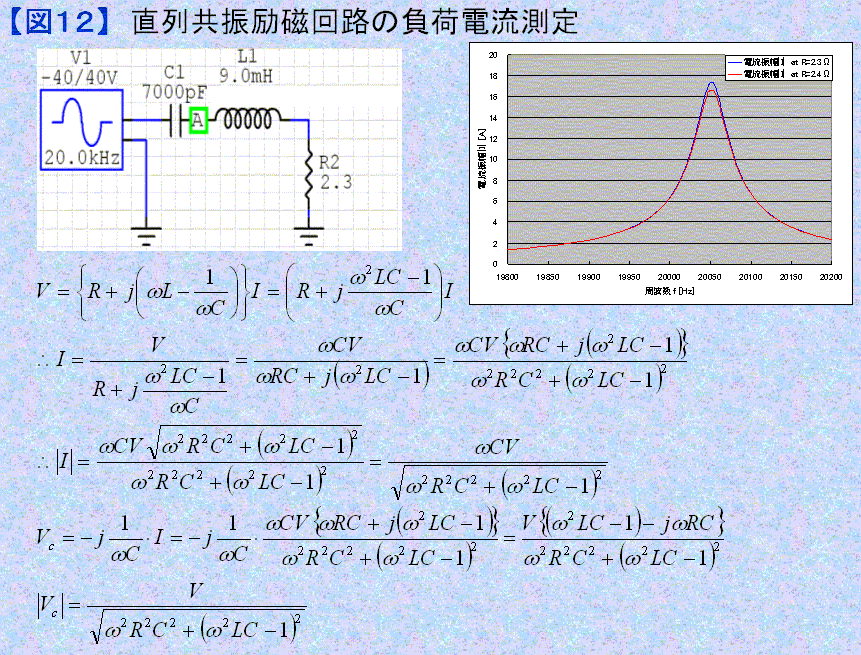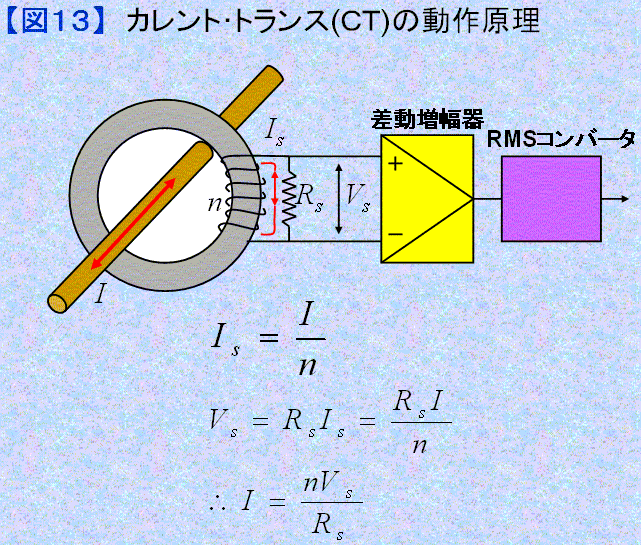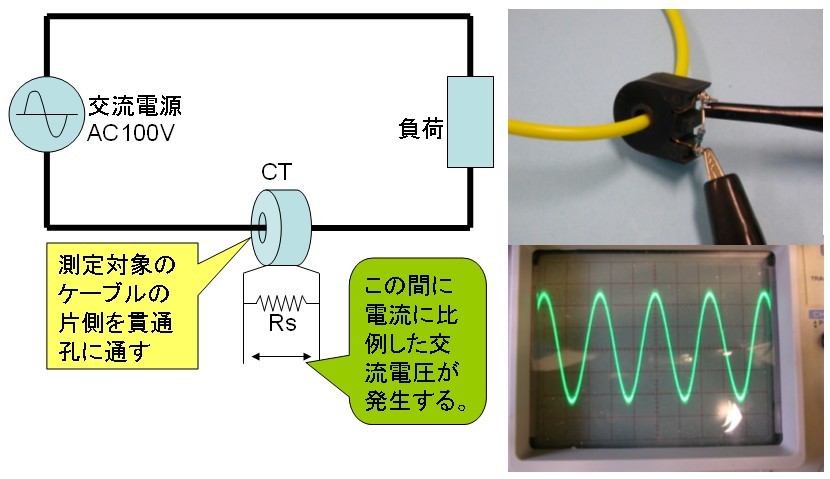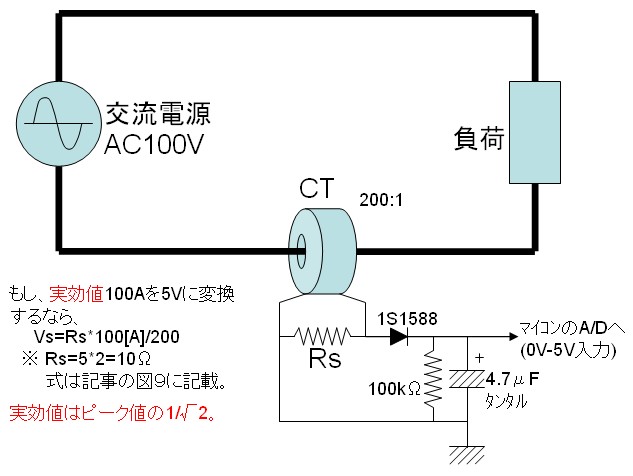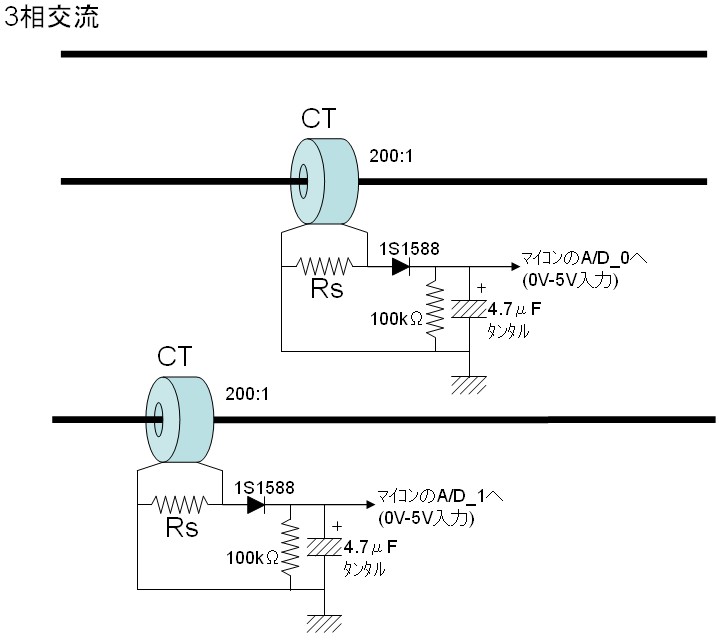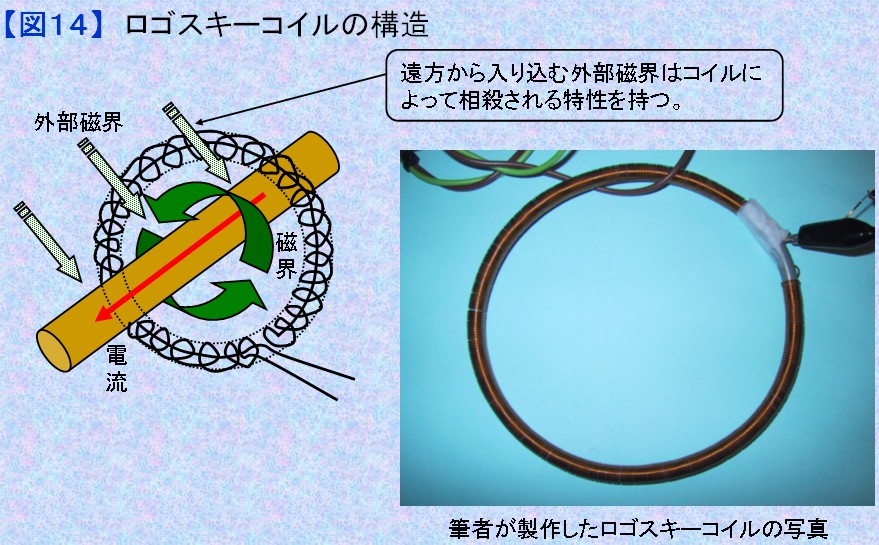|
|
【ブラウザはGoogle Chrome】
●最新版ダウンロードはこちら 【お知らせ】Windows7でChromeがフリーズを起こす場合は、コントロールパネル⇒管理ツール⇒サービス でWindows Media Player Network Sharing Serviceを停止かつ無効にします。Micorosoftのバグです。 |
||
当サイトはSPAM対策等のためJavaScriptを使っています。
JavaScriptの実行を可能な状態にしてご利用下さい。
Please enable the execution of JavaScript!